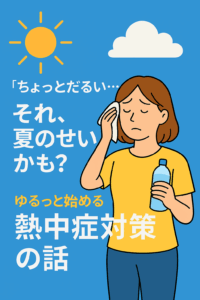福岡県大野城市にある「株式会社障がい者つくし更生会」は、障害のある方々が中心となって運営している、全国的にも珍しい会社です。1984年に設立されてから40年近く、市のごみ処理業務を担いながら、地域社会とともに歩んできました。現在では、従業員38名のうち31名が障害のある方で、その障害の種類もさまざまです。
設立のきっかけは、創業者である小早川さんの想いからでした。小早川さん自身も若いころに結核を患い、後遺症によって障害者となった経験からだそうです。そしてその中で、健常者と同じように働くことの難しさ、そして仕事を得ることの困難さを痛感したそうです。
そんな中、「障害のある人が自ら働ける会社をつくりたい」という強い願いを持ち、約1,000万円の資金を、障害者や支援者といった仲間たちとともに集めて会社を立ち上げました。
つくし更生会では、不燃ごみの分別やペットボトルの選別など、多くの現場で障害のある方が活躍しています。たとえば、ビンや缶を手作業で色別に分ける作業や、破砕機を操作する重機の運転、さらには市民と直接やり取りを行う受付業務なども担当しています。事務の仕事においても、視覚障害や身体障害のある方が、パソコンや点字ディスプレイなどの支援機器を活用しながら丁寧に取り組まれています。
印象的なのは、障害の種類や重さで仕事を分けていないという点です。誰にでも得意・不得意があることを前提に、一人ひとりの適性や希望を尊重した配置が行われています。その結果、重度の障害を持ちながらも、資格を取得して機械を操作したり、他の人に作業を教えたりする方も多くいらっしゃいます。
この会社のもうひとつの魅力は、「教える文化」が根付いていることです。新しく入ってきた実習生や見学者には、障害のある従業員自らが案内をしたり、作業の説明を行ったりしています。「どうやって説明すれば伝わるか」と考えることで、自分の理解も深まり、仕事への誇りも生まれています。
また、精神障害を持つIさんのエピソードも心に残ります。かつては障害を隠して複数の職場で働いていましたが、うまくいかず、つくし更生会に入社されました。入社後は、周囲の理解あるサポートと、「まず人として向き合う」という社風の中で、徐々に居場所を見つけ、自信を取り戻していったそうです。現在では、仲間のために手話を学び、積極的にコミュニケーションを取るなど、自分にしかできない役割を見つけて働かれています。
つくし更生会の取り組みは、「障害があるからできない」という社会の偏見を静かに、しかし力強く打ち破っています。特別な支援専門家がいなくても、誰もが尊重される環境で、主体的に働くことは可能です。むしろ、“素人だからこそわかる感覚”を大切にしながら、自然な関わりの中で、お互いに支え合える職場を築いているのだと感じました。
障害のある・なしにかかわらず、誰もが誇りを持って働ける社会とは、どのようなものでしょうか。私たちが何気なく過ごしている日常の中にも、少しの工夫と理解があれば、きっと誰かの「働きたい」を支えることができるのではないでしょうか。
あなたのまわりには、そんな“誰か”がいるかもしれませんね。
ご希望があれば、この文章に合うブログタイトルやアイキャッチ画像の提案もできます。お気軽にお申し付けくださいね。